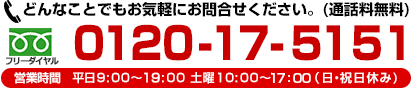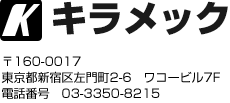伝統の法被の柄について
デザインの参考になる!伝統的なはっぴの柄をご紹介いたします。知っておいて損はない、柄についての豆知識は法被製作にきっと活かせるはずです。
法被の模様と歴史
江戸時代に幕府から出された、倹約を推奨・強制するための奢侈禁止令や格安で綿花が入手可能になったことで、ハンテンは江戸時代に急速に普及しました。同時に染色技術も飛躍的に進歩し、多様な模様をプリントできるようになりました。江戸時代には半纏に印刷された屋号、模様、文字などから、人物の職業や身分が一目瞭然であったとされています。
腰柄と総柄について
-
- 【腰柄とは】
- 腰柄はその名のとおり、法被の前身頃と後ろ身頃の腰周りに施されたデザインを指します。様々な種類があり、現代でも残っているデザインがあります。

-
- 【総柄とは】
- はっぴ全体にデザインが施されているものを総柄と呼びます。躍動感があって、強く心に刻まれるデザインが特徴です。主流のデザインには、沙綾型・二の字・麻の葉・熨斗・桜などがあります。

主な法被の模様
-
- 【吉原つなぎ】
- 四隅を少しくぼませた四角形をつなぎ合わせた、鎖のようなデザインが特徴。吉原遊郭に一度入ると、なかなか開放されないことにちなんだ名前とも言われています。半纏に限らず、現在でも手ぬぐいや風呂敷など様々な製作シーンで活用されています。

-
- 【波柄】
- 勢いと清涼感がある波を描いた柄。何度も押し寄せてくる勢いのある波は、岩の形をも変える事から不退転の強い意志や波に乗って成功へ導くなど様々な意味や想いが込められています。勢いをつけて成功するようにという願いを込めて販促キャンペーンなどに採用されることが多い柄です。

-
- 【青海波】
- 扇状に波をデフォルメしたデザインを重ねた幾何学模様。穏やかに波が広がるのように、平穏な暮らしが永遠に続いて欲しいという願いを込めて製作されたともいわれています。

-
- 【市松】
- 江戸時代の歌舞伎役者・初代佐野川市松が考案したオリジナルデザイン。歌舞伎の舞台衣装に用いたことで、人気が広まったといわれている模様です。別名「市松模様」「市松格子」「元禄模様」などとも呼ばれています。

-
- 【だんだら模様】
- 新選組の隊服などに用いられた三角形の白い模様は「だんだら模様」といいます。元々は「だんだら模様」は『忠臣蔵』の「赤穂浪士」が吉良邸討ち入りのときに着ていた羽織の柄であり、それを新選組局の近藤勇が、赤穂浪士の忠義のあり方に感銘を受けて隊服に採用した経緯があるそうです。












































































 オーダー法被の専門店
オーダー法被の専門店 名入れ提灯の専門店
名入れ提灯の専門店 オリジナル扇子の専門店
オリジナル扇子の専門店 オーダーのれんの専門店
オーダーのれんの専門店 のぼり作成の専門店
のぼり作成の専門店 展示会・イベントテーブルクロスの専門店
展示会・イベントテーブルクロスの専門店