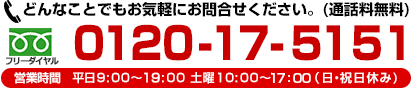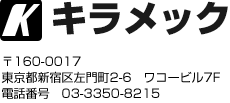扇子の歴史と茶道との関わりについて

扇子と茶道には長い歴史によって築かれた、切り離すことができない密接な関係があります。
扇子は平安時代頃から日本で使用されていたといわれており、この頃から既に、本来の用途である扇いで涼をとるための道具としてだけでなく、扇子に和歌を書いたり花を載せ、贈答・儀礼・コミュニケーションのツールとしても用いられていました。
また武士にとって扇子は刀と同等の物と解釈され、尊ばれていたということもあり、扇子を携える場合は、刀と同様に左の腰に差すというマナーが確立したともいわれています。
そして、鎌倉時代には、日本の扇子が中国に渡り、両面貼りの扇子が作られ、室町時代に日本に逆輸入された物が普及します。
更に時が経つにつれて、扇子は茶道・能・演劇などの様々な場面で、扇面の絵柄やサイズが異なる、茶扇や能扇と呼ばれる専用の道具として用いられるようになり、やがて時代が江戸になると庶民の生活必需品としても定着するようになるのです。
表千家の扇子

現代の茶道の祖とされる、「わび茶」を発展させた茶人である千利休の子孫たちが作った「三千家」と呼ばれる、代表的な茶道の流派の一つ表千家。
千家の家督を継いだ千家流茶道の本家ともいわれる表千家でも、扇子は重要な役割を果たします。
ここでは、表千家で使用される扇子の特徴や扱い方をご紹介したいと思います。
1.種類
表千家では、室町時代以降、茶道の発展とともに茶席で用いられるようになった、茶扇(ちゃせん)と呼ばれる特定の形式を持った扇子が使用されます。
2.サイズ
表千家では、男女共に「6.5寸(約19.7cm)」の扇子を使用します。
尚、「三千家」のうちの一つである、裏千家で使用する扇子は、男性は6寸、女性は5寸(約15.2cm)と微妙に寸法が異なります。
3.扱い方
茶扇は、茶室に入る際から最後まで手に握っているか、畳の上に置いているかのどちらかになります。
挨拶や拝見の際には、ひざの前に扇子を置いて、両手をついて挨拶をします。
尚、お茶室の外などで扇子を使わないときは、帯の中に入れておきます。帯への扇子の入れ方については、自分の立場が亭主かお客かで異なり、更には流派によっても作法がまちまちです。詳細については、お稽古の際など、事前に先生に直接確認しておくことをオススメします。
4.扇子の骨の色
表千家で使用する茶扇の骨には、大きくわけて親骨が白い(白竹)ものと漆などで染められた黒塗りのものがあります。
どちらも宗匠が使用していることから、ご自身の好みに合わせて選ぶことが可能です。
一般的には黒塗りは格式が高い印象を与えるので、華やかな席で使用されることが多いです。一方で、白竹は風情があり、小間の茶事などでよく愛用されています。他にも、染められた扇子は玄人向けのものという印象があるため、迷った場合は白竹を買っておくのが無難という意見もあります。
扇子を購入する際には、「茶扇の扱い方」と同様に、事前に先生や先輩方に直接確認しておくことを推奨します。
扇子の作法

茶道用語には「結界」という言葉があります。
結界とは人や道具の間に作る境界のことを指し、相手と自分との間に境界を作ることで、相手を敬い自分がへりくだるという意味が込められます。
扇子は「結界」をつくるための道具として、挨拶をする際や茶室に入るとき、道具を拝見するときなどにも、着座した自分のひざの前に必ず置かなくてはなりません。このように、扇子は茶道やお茶会で欠かすことができないとても重要な役割を担っているのです。
このような、茶室への入室や挨拶の際に扇子を着座した自分のひざの前に置くというマナーは、茶道がもてはやされた戦国時代に、武将たちが茶室に入る際に刀を扇子に持ち替えて、相手の前に差し出すことで、相手に対して敵意がないという意志を表す行為の名残りだという説もよく耳にする話です。
ちなみに、余談ですが、本来茶道に必要な持ち物は、以下の7点だといわれています。
■茶道に必要なアイテム7点
- 扇子(せんす)
- 懐紙(かいし)
- 楊枝(ようじ)
- 帛紗(ふくさ)
- 古帛紗(こぶくさ)
- 楊枝入れ(ようじいれ)
- 帛紗ばさみ(ふくさ)
しかし、もし仮にあなたがどうしても欠席できないお茶会に急遽お呼ばれした場合、最低限以下の3点を用意していけば、大体の場合はなんとかなるはずです。
■急ない茶会のお呼ばれで最低限必要なアイテム3点
- 扇子(せんす)
- 懐紙(かいし)
- 楊枝(ようじ)
近年では、扇子(せんす)・懐紙(かいし)・楊枝(ようじ)の3点は100円ショップでも揃えることができるので、最寄りのお店へ是非お運びください。
まとめ

扇子は茶道の雰囲気を引き立てる重要なアイテムです。
流派に合わせ、茶扇選びにもこだわり、正しい扱い方を心得れば、より深く茶道の世界に没入し、愉しむことができるはずです。
キラメックでは、流派に合わせたオリジナル茶扇のオーダーメイド製作も承っております。お客様からのご質問やご相談も随時受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
↓↓↓↓↓↓↓






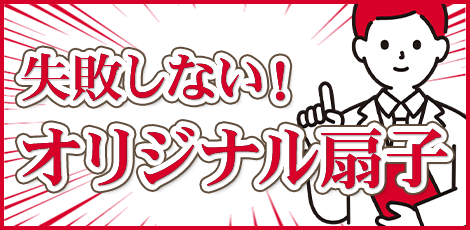



















 オーダー法被の専門店
オーダー法被の専門店 名入れ提灯の専門店
名入れ提灯の専門店 オリジナル扇子の専門店
オリジナル扇子の専門店 オーダーのれんの専門店
オーダーのれんの専門店 のぼり作成の専門店
のぼり作成の専門店 展示会・イベントテーブルクロスの専門店
展示会・イベントテーブルクロスの専門店